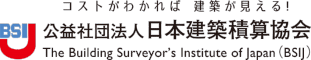学校教育について
Outline
学生が社会に巣立った時、多様な建築生産活動に対応できる建築積算の知識と技術が役立ちます。建築積算は、建築生産活動の経済行為を支える基本的な知識と技術であり、いかなる設計(デザイン)も施工(技術)も建築積算(コスト)なしには実現できません。
建築を学んだ学生は、卒業後さまざまな分野で業務にたずさわりますが、建築積算から学ぶ知識と技術は、経済行為を重視する実社会で大変有意義なものとなります。
公益社団法人日本建築積算協会は、学生向けにわかりやすいテキストを開発するとともに、要請があれば当協会認定の講師を派遣しています。
また当協会作成のテキストによる教育を受講し、単位取得後、当協会実施の試験に合格し、登録を申請した人には、建築積算士補の資格が付与されます。
建築積算士補は、建築積算士に次ぐ資格であり、取得者は建築積算士の一次試験が免除されます。
建築積算士補は、学生が取得できる数少ない技術資格であり、就職時に役立てることができます。
学校教育の実施状況
2024.04現在
| 大学 | 高専 | 高校 | 専門学校 | その他 (職業訓練等) |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年度 | 13 | 1 | 7 | 17 | 17 | 55 |
| 2016年度 | 12 | 1 | 6 | 15 | 16 | 50 |
| 2017年度 | 12 | 1 | 10 | 16 | 18 | 57 |
| 2018年度 | 13 | 1 | 10 | 17 | 19 | 60 |
| 2019年度 | 14 | 1 | 11 | 17 | 19 | 62 |
| 2020年度 | 14 | 1 | 11 | 17 | 19 | 62 |
| 2021年度 | 14 | 1 | 11 | 17 | 18 | 61 |
| 2022年度 | 15 | 1 | 10 | 17 | 17 | 60 |
| 2023年度 | 15 | ― | 9 | 17 | 17 | 58 |
| 2024年度 | 15 | ― | 6 | 17 | 17 | 55 |
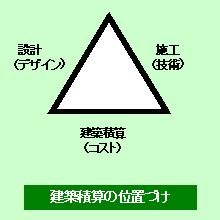
建築生産活動は、下図に示すように設計、施工、建築積算のトライアングルで成り立っており、建築積算は、建築物のコストを算定する上で重要な役割を担っています。
一般に建築は設計や施工などの分野がよく知られていますが、いかなるデザインや施工技術も経済的な裏づけなしには実現できません。
建築生産は経済活動であり、建築物のコストを算定する知識と技術は、設計者や施工者をはじめ建築に関係するすべての人に求められます。
しかしながら学校における建築コスト教育は、これまで不十分であったことは否めません。
現在は即戦力となる人材が求められ、当協会は積算分野の専門家団体として支援します。
特に最近の建設業においては、耐震偽装、品質、安全、環境等の問題が多発し、一般の国民からの信頼を失っていますが、これらの根底には不透明な建築コストの問題があります。
建築系の卒業生は就職先が多様化しています。卒業後いかなる職場においても建築積算の知識と技術を学生の時に学習しておく意義は大きいといえましょう。
建築積算を専門とする技術者は、下表に示すような知識や技術を実務を通して身につけていきます。
特に建築数量の計測・算出の知識や技術を習得することにより、図面の読解力が飛躍的に身に付き、図面や仕様書のミスや不整合が分かるようになります。
また使用される資材や機材の知識だけでなく、工構法や施工方法にも通じるようになり、施工管理や専門工事の担当者との折衝能力が高まります。
その結果、幅広い分野で活躍が可能となり、CMrやPMrなどへのキャリアアップが実現します。
| 1. 建築数量の計測・算出 |
| 2. 見積書の作成、評価 |
| 3. 設計図面の解読、不整合や誤りの指摘 |
| 4. 各種仕様書の解読 |
| 5. 工事の推測・可能性判断 |
| 6. 建築資材、機材の知識 |
| 7. 各種単価および相場の知識 |
| 8. 工構法や施工方法の知識 |
| 9. 専門工事の理解、業者との折衝能力 |
| 10. 数量統計、概算 |
| 11. パソコンやインターネットの活用能力 |